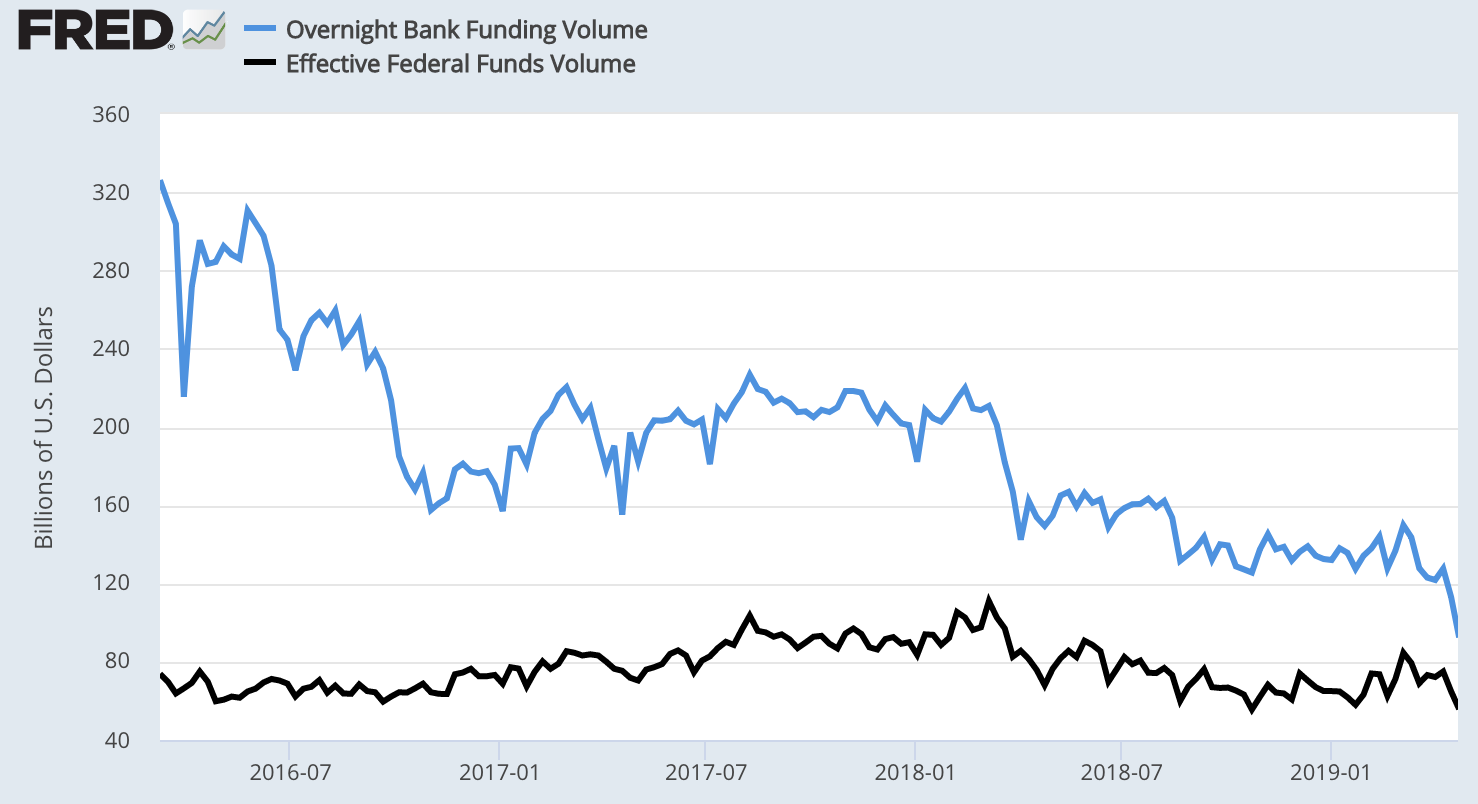今回ジョン・ベイツ・クラーク賞を受賞したエミ・ナカムラの業績を「The Price of Everything, the Value of the Economy: A Clark Medal for Emi Nakamura!」と題したエントリでA Fine Theoremブログが紹介している(H/T Economist's View)。
以下はそこからの引用。
Namakura ... has built insane price datasets, come up with clever identification strategies to separate pricing models, and used these tools to vastly increase our understanding of the interaction between price rigidities and the business cycle. Her “Five Facts” paper uses BLS microdata to show that sales were roughly half of the “price changes” earlier researchers has found, that prices change more rapidly when inflation is higher, and that there is huge heterogeneity across industries in price change behavior. Taking that data back to the 1970s, Nakamura and coauthors also show that high inflation environments do not cause more price dispersion: rather, firms update their prices more often.
(拙訳)
ナカムラは・・・とんでもない価格データセットを構築し、価格モデルを取り出す巧妙な識別戦略を考案し、それらの道具を用いて価格硬直性と景気循環の相互作用に関する我々の理解を大いに深めた。彼女の「5つの事実」論文は、労働統計局のミクロデータを用いて、セールスが従来の研究者の見い出した「価格変化」のおよそ半分を占めること、価格変化はインフレ率が高いほど急であること、価格変化の行動は業種によって大いに異なることを示した。そのデータを1970年代まで遡り、ナカムラと共著者はまた、高インフレ環境によって価格のばらつきが大きくなるわけではないことを示した。むしろ、企業の価格の更新頻度が高くなるのである。
Though generally known as an empirical macroeconomist, Nakamura also has a number of papers, many with her husband Jon Steinsson, on the theory of price setting. For example, why are prices both sticky and also involve sales? In a clever paper in the JME, Nakamura and Steinsson model a firm pricing to habit-forming consumers. If the firm does not constrain itself, it has the incentive to raise prices once consumers form their habit for a given product.... To avoid this time inconsistency problems, firms would like to commit to a price path with some flexibility to respond to changes in demand. An equilibrium in this relational contract-type model involves a price cap with sales when demand falls: rigid prices plus sales, as we see in the data! In a second theoretical paper with Steinsson and Alisdair McKay, Nakamura looks into how much communication about future nominal interest rates can affect behavior. In principle, a ton: if you tell me the Fed will keep the real interest rate low for many years (low rates in the future raise consumption in the future which raises inflation in the future which lowers real rates today), I will borrow away. Adding borrowing constraints and income risk, however, means that I will never borrow too much money: I might get a bad shock tomorrow and wind up on the street. Giving five years of forward guidance about interest rates rather than a year, therefore, doesn’t really affect my behavior that much: the desire to have precautionary savings is what limits my borrowing, not the interest rate.
(拙訳)
実証マクロ経済学者として一般に知られているが、ナカムラは価格設定の理論に関する論文も数多く著しており、その多くは夫のジョン・スタインソンとの共著である。例えば、なぜ価格は粘着的であると同時にセールスを伴うのか? 巧みなJME論文でナカムラとスタインソンは、習慣形成的な消費者に対する企業の価格付けをモデル化した。企業は、自らを抑制しなければ、ある商品について消費者が習慣を形成すると価格を引き上げるインセンティブを持つ。・・・この時間的不整合の問題を回避するため、企業は、需要の変化に対応する幾らかの柔軟性を持つ価格経路にコミットしたいと考える。この関係的契約型モデルにおける均衡は、価格上限と、需要が低下した時のセールスを伴う。即ち、セールスを伴う硬直的な価格であるが、これは我々がデータに見る通りのものである! スタインソンとアリスダー・マッケイとの2番目の理論論文では、将来の名目金利に関するコミュニケーションがどの程度人々の行動に影響するかを調べた。原理的には、大いに影響する。FRBが実質金利を長期に亘って低く保つと知ったならば、私は金を借りっぱなしにするだろう。しかし、借入制約と所得リスクを付け加えると、私は過剰に借り入れないことになる。明日悪しきショックを受けて失業するかもしれないからだ。従って、1年先ではなく5年先の金利のフォワードガイダンスを提示しても、私の行動にそれほど影響しないことになる。金利ではなく、予備的貯蓄を持ちたいという欲求が私の借り入れを制約するからだ。
...luckily Nakamura has two great easily-readable summaries of her core work. First, in the Annual Review of Economics, she lays out the new empirical facts on price changes, the attempts to identify the link between monetary policy and price changes, and the implications for business cycle theory. Second, in the Journal of Economic Perspectives, she discusses how macroeconomists have attempted to more credibly identify theoretical parameters. In particular, external validity is so concerning in macro – remember the Lucas Critique! – that the essence of the problem involves combining empirical variation for identification with theory mapping that variation into broader policy guidance. I hesitate to stop here since Nakamura has so many influential papers, but let us take just more quick tasters that are well worth your more deep exploration. On the government spending side, she uses local spending shocks and a serious model to figure out the national fiscal multiplier from government spending. Second, she recently has linked the end of large-scale increases in female moves from home production to the labor force has caused recessions to last longer.
(拙訳)
・・・幸運なことに、ナカムラは彼女の中心的な仕事についての読みやすい素晴らしい要約を2つ出している。一つはアニュアルレビューオブエコノミクスに掲載したもので、そこで彼女は、価格変化に関する新たな実証的事実、金融政策と価格変化の関係を識別しようとする試み、そしてその景気循環にとっての意味合いを解説している。二つ目はジャーナルオブエコノミックパースペクティブズに掲載したもので、そこで彼女は、マクロ経済学者がいかに理論パラメータの識別の信頼性を高めようとしてきたかを論じている。特に、外的妥当性はマクロ経済学にとって大いなる関心事項であるため――ルーカス批判を想起されたい!――識別のための実証上の変動と、その変動をより広範な政策指針に反映させる理論とを結びつけることが問題の中心にある。ナカムラは非常に多くの影響力のある論文を書いているので、まだエントリを終えたくないのだが、読者がもっと深く追究する価値が十分にある研究をもう少しざっと紹介しておこう。政府支出について彼女は、地方政府の支出ショックと、きちんとしたモデルを用いて、国の政府支出の財政乗数を推計した*1。また最近彼女は、女性が家庭での生産活動から労働力へと大規模に移行することが終了したことと、景気後退が長引くようになったことを、因果関係として関連付けた。
A Fine Theoremブログは、冒頭で、今回の受賞がマクロ経済学者にとってアンドレイ・シュライファー以来20年ぶりであることを強調している(ちなみに昨年同ブログは、ナカムラなど気鋭のマクロ経済学者が受賞していないことで同賞を批判している)。ただ、偏狭な視点という誹りを覚悟で言うならば、我々日本人にとっては日本の姓を持つ人が同賞を受賞したことのインパクトもそれに負けず劣らず大きいような気がする*2。
ちなみに本ブログのこれまでのナカムラ論文関連エントリは以下の通り。
himaginary.hatenablog.com
himaginary.hatenablog.com
himaginary.hatenablog.com
himaginary.hatenablog.com
himaginary.hatenablog.com
himaginary.hatenablog.com
himaginary.hatenablog.com